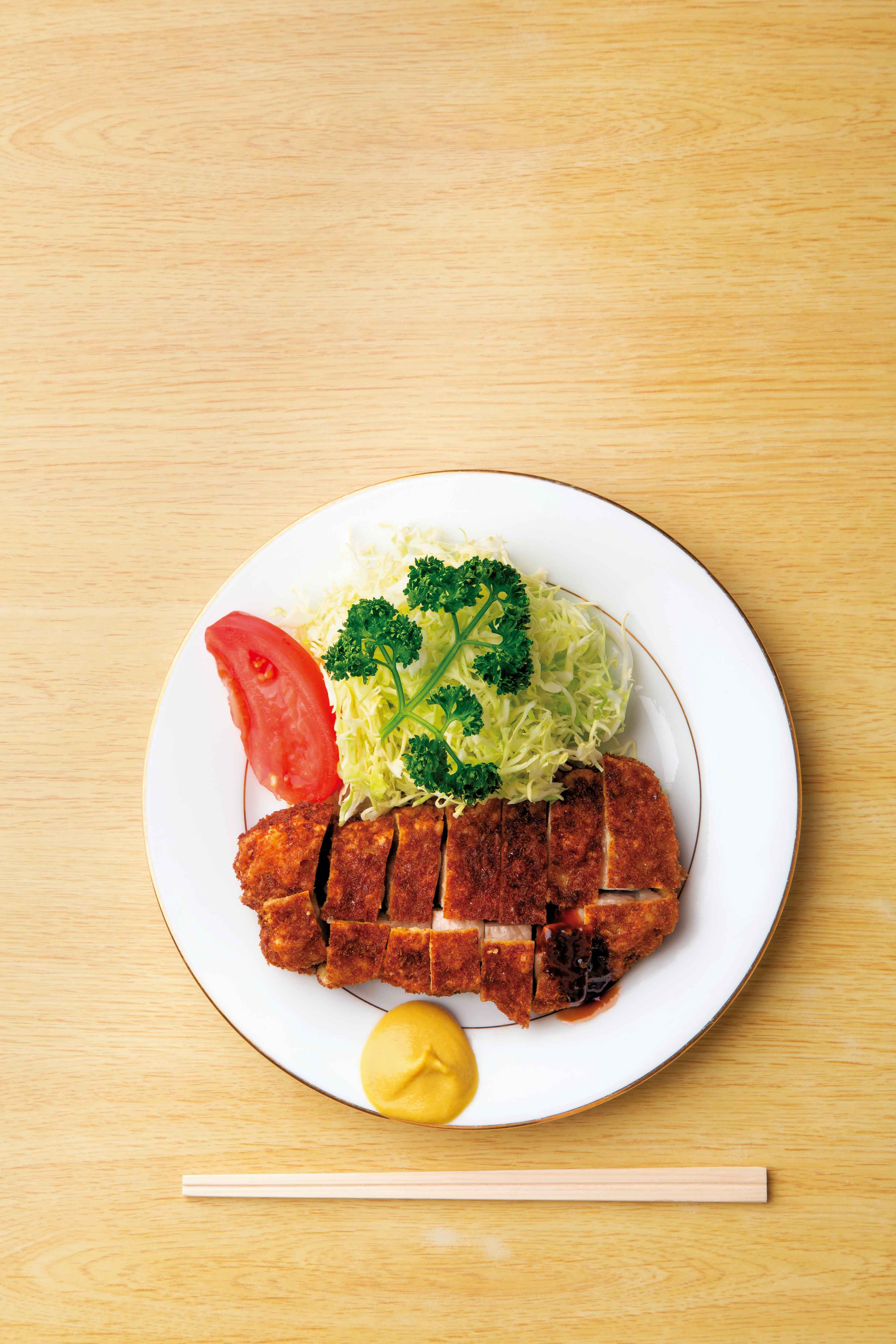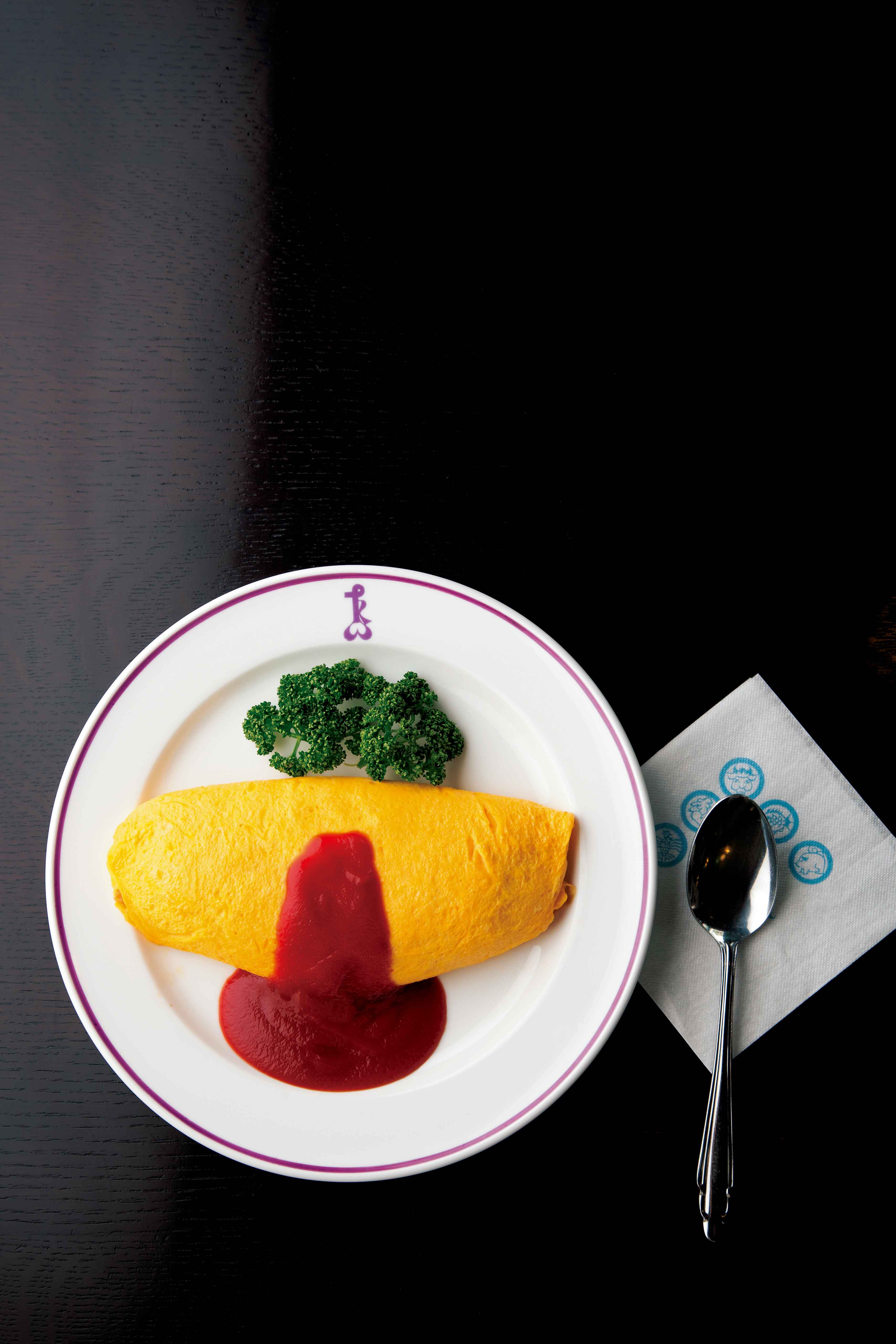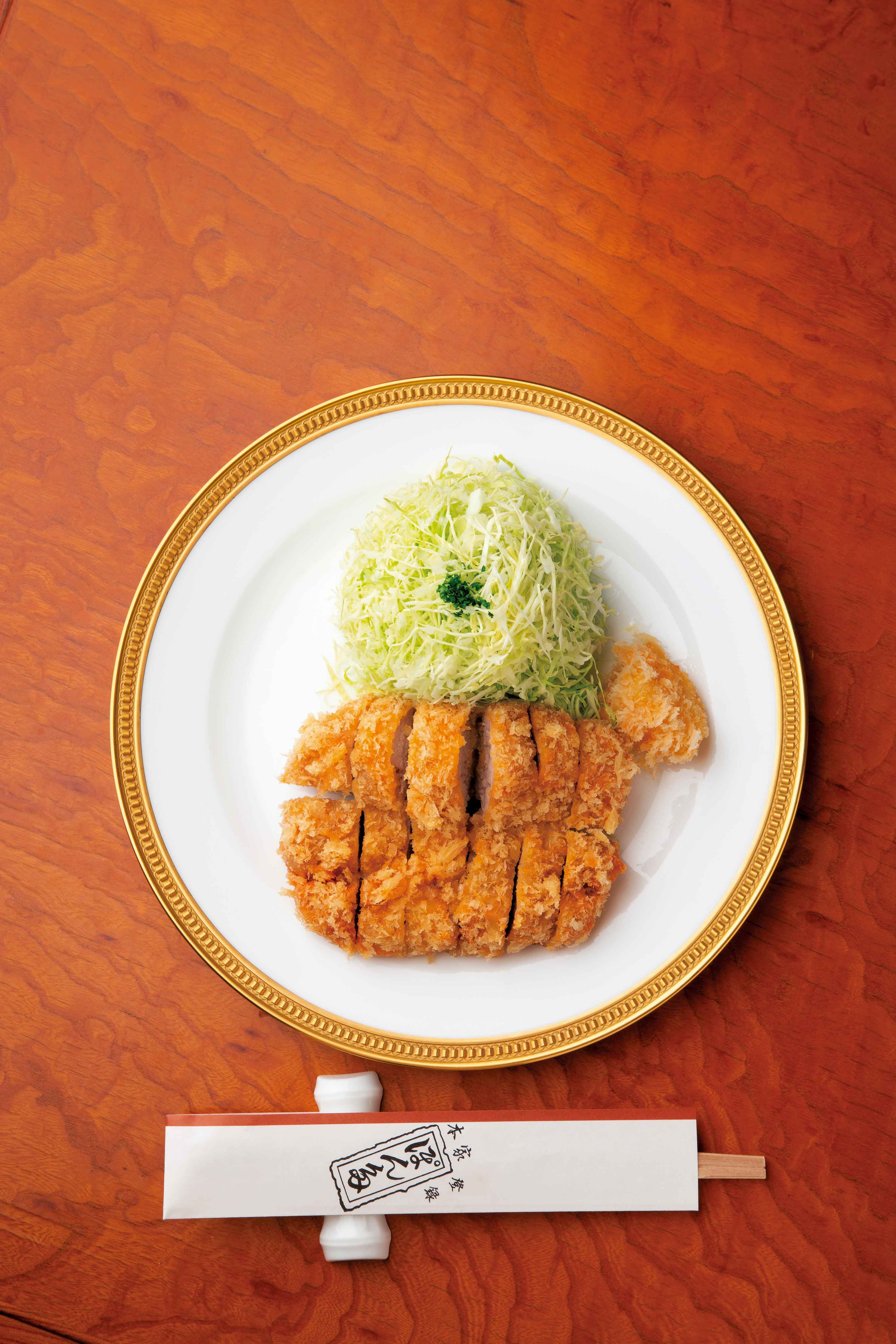初夏の走りにだけ店に並ぶ水ようかんや、バタークリームを使ったフランス菓子、甘さと塩気のバランスが絶妙な大福…。こんなおやつが3時に出てきたら、どんなにうれしいことでしょう。作家や文化人たちにとってのおやつは、季節の訪れを告げるものであり、暮らしにささやかな悦びをもたらすものでもありました。
昭和の味第4弾は、そんな彼らを魅了した〝昭和のおやつ〟。往時と変わらぬ心意気で、生真面目につくられている逸品の数々をご紹介しましょう。
写真/東京・青山にある和菓子店「菊家」に飾られている写真。この店の菓子をとりわけ贔屓にしていた作家・向田邦子(むこうだくにこ)が、先代女将と語らう姿が写し出されています。
昭和の味第4弾は、そんな彼らを魅了した〝昭和のおやつ〟。往時と変わらぬ心意気で、生真面目につくられている逸品の数々をご紹介しましょう。
写真/東京・青山にある和菓子店「菊家」に飾られている写真。この店の菓子をとりわけ贔屓にしていた作家・向田邦子(むこうだくにこ)が、先代女将と語らう姿が写し出されています。
RELATED STORY

川端康成、白洲正子、織田作之助が通った名店を訪ねて
ようかんに恋した女流俳人
中村汀女を魅了した3つのようかん
昭和のころ、お客様にお出しする菓子といえば、筆頭にあがるのがようかんでした。充実した甘さ、日本茶との相性のよさもありますが、今より流通が発達していなかったあのころ、日もちのするようかんは、来客の多い家には欠かせないものでもあったのです。
気どりのない言葉で、愛情のこもった句を詠んだ俳人・中村汀女(なかむらていじょ)。酒が一滴も飲めなかったこともあって、甘いおやつには目がありませんでした。
「ようかんの切り方のむずかしさよ、心のいることよ。(略)厚目にとはずんだ心意気は、これはわが胸だけが知ること。そしてまたなんと満ち足ることか。好きな客に出すのなら尚更だが、仕事終えた一休みに、自分自身に切る一きれにしてまたうれしいかぎりである」(「秋袷」―『あまカラ抄 3』冨山房百科文庫に所収―より。以下同)と、特に愛したのがようかん。味や切り方に加え、「食べて始末がいい、最後まで形がくずれない」と褒め、「ほんとはあの厚みを手にとってたべたい。煉りのほども、手にとってじかに口にするときが一番よくわかる気がする」とまで綴っています。

そんな汀女が推薦文を寄せるほど気に入っていたのは、兵庫県・龍野にある老舗『吾妻堂』の煉りようかん(写真上)。その姿と色を「沈んださくら色。(略)なかなかの品格です」と呼び、「私は〝もどりかけ〟の角の堅いようかんが好きなものですから、これは私向きです」と記しています。
『吾妻堂』の練りようかんは、収穫にも下ごしらえにも手間のかかる貴重な素材である播州地方産のササゲ豆を使用。また、岐阜県産の天日干し寒天を使っているため、食べると歯がめりこむほどに練りが強いのも特徴です。
「汀女が書いた〟もどりかけ〟というのは、練った熱いようかんがゆっくり固まる過程でザラメが結晶化し、シャリシャリとした歯触りになる状態です。毎日午後から練りだけに専念し、ひと晩かけて固めるため、結晶がつくのです」
と四代目。汀女の言う品格とは、つくり手の、愚直なまでの一生懸命さを指すのかもしれません。

いっぽう、食べ方も含めて愛し、何日にもわたってその風味を楽しんだのは、岐阜県『「金木戸屋(かなきどや)』の笹巻ようかん(写真上)。「キャラメルの紙をむいてもうれしいものを、こんな豪華な包紙をほどいていいというのは大人の特権」(『ふるさとの菓子』丸善より抜粋。以下同)と、汀女らしいユーモアをこめて綴っています。〝包紙〟とは、アルプス山麓の熊笹のこと。この銘菓は、笹を折り曲げたところへ直接ようかん液を注ぎ、固めたものなのです。「深山の熊笹の匂いがようかんの芯までに及んでいようというもの。中味は日を経てかえって甘味をととのえ、とろりと溶ける」と、味と風味を存分に楽しみました。

また、「二つ割りの青竹に、透き通る柿の色、切り出して半月の形となる」と愛おしんだのが、西美濃の干し柿を原料とした柿ようかん(写真上)。宝暦5(1755)年創業の老舗『御菓子つちや』の看板商品は、まさに柿そのもの甘さです。「日が経って表面に浮く薄氷(うすらい)のような結晶にも、まさしく富有柿の甘みが溶けている」と、ここでも〝ようかんの結晶好き〟な一面がよく表れています。

写真/昭和を代表する俳人のひとり、中村汀女。「女にとって菓子とは(略)恋人」と言い、甘いものにまつわる俳句も多く詠んだ。(写真提供:文藝春秋)
気どりのない言葉で、愛情のこもった句を詠んだ俳人・中村汀女(なかむらていじょ)。酒が一滴も飲めなかったこともあって、甘いおやつには目がありませんでした。
「ようかんの切り方のむずかしさよ、心のいることよ。(略)厚目にとはずんだ心意気は、これはわが胸だけが知ること。そしてまたなんと満ち足ることか。好きな客に出すのなら尚更だが、仕事終えた一休みに、自分自身に切る一きれにしてまたうれしいかぎりである」(「秋袷」―『あまカラ抄 3』冨山房百科文庫に所収―より。以下同)と、特に愛したのがようかん。味や切り方に加え、「食べて始末がいい、最後まで形がくずれない」と褒め、「ほんとはあの厚みを手にとってたべたい。煉りのほども、手にとってじかに口にするときが一番よくわかる気がする」とまで綴っています。

そんな汀女が推薦文を寄せるほど気に入っていたのは、兵庫県・龍野にある老舗『吾妻堂』の煉りようかん(写真上)。その姿と色を「沈んださくら色。(略)なかなかの品格です」と呼び、「私は〝もどりかけ〟の角の堅いようかんが好きなものですから、これは私向きです」と記しています。
『吾妻堂』の練りようかんは、収穫にも下ごしらえにも手間のかかる貴重な素材である播州地方産のササゲ豆を使用。また、岐阜県産の天日干し寒天を使っているため、食べると歯がめりこむほどに練りが強いのも特徴です。
「汀女が書いた〟もどりかけ〟というのは、練った熱いようかんがゆっくり固まる過程でザラメが結晶化し、シャリシャリとした歯触りになる状態です。毎日午後から練りだけに専念し、ひと晩かけて固めるため、結晶がつくのです」
と四代目。汀女の言う品格とは、つくり手の、愚直なまでの一生懸命さを指すのかもしれません。

いっぽう、食べ方も含めて愛し、何日にもわたってその風味を楽しんだのは、岐阜県『「金木戸屋(かなきどや)』の笹巻ようかん(写真上)。「キャラメルの紙をむいてもうれしいものを、こんな豪華な包紙をほどいていいというのは大人の特権」(『ふるさとの菓子』丸善より抜粋。以下同)と、汀女らしいユーモアをこめて綴っています。〝包紙〟とは、アルプス山麓の熊笹のこと。この銘菓は、笹を折り曲げたところへ直接ようかん液を注ぎ、固めたものなのです。「深山の熊笹の匂いがようかんの芯までに及んでいようというもの。中味は日を経てかえって甘味をととのえ、とろりと溶ける」と、味と風味を存分に楽しみました。

また、「二つ割りの青竹に、透き通る柿の色、切り出して半月の形となる」と愛おしんだのが、西美濃の干し柿を原料とした柿ようかん(写真上)。宝暦5(1755)年創業の老舗『御菓子つちや』の看板商品は、まさに柿そのもの甘さです。「日が経って表面に浮く薄氷(うすらい)のような結晶にも、まさしく富有柿の甘みが溶けている」と、ここでも〝ようかんの結晶好き〟な一面がよく表れています。

写真/昭和を代表する俳人のひとり、中村汀女。「女にとって菓子とは(略)恋人」と言い、甘いものにまつわる俳句も多く詠んだ。(写真提供:文藝春秋)
龍野『吾妻堂』の練りようかん
汀女が「沈んださくら色」と呼んだ煉りようかんは、一日に4寸のもので100本しかつくれない。龍野は、童謡「赤とんぼ」の舞台となった川縁が広がる詩情豊かな町。昭和5(1930)年、二代目が現在の地に店を構えたころの雰囲気を今も残している。●兵庫県たつの市龍野町下川原52  0791-63-0140
0791-63-0140
 0791-63-0140
0791-63-0140飛驒『金木戸屋』の笹巻羊羹
昭和6(1931)年、飛驒の老舗菓匠が創案した郷土色豊かなようかん。昔は山で水を飲むときに笹を折り曲げて器にした…という話をヒントにつくったもの。天然の熊笹を開くと、笹の移り香と葉脈がくっきりとついた小豆羊羹が現れる。レトロなパッケージも魅力。●岐阜県飛驒市神岡町船津1077-1  0758-82-0172
0758-82-0172
 0758-82-0172
0758-82-0172大垣『御菓子つちや』の柿羊羹
美濃の城下町・大垣の老舗店でつくられる柿羊羹は、創作以来170年の銘菓。原料は、渋柿の最高級品・堂上蜂屋柿(どうじょうはちやがき)を天日干ししたもの。干し柿特有の素朴な甘みが懐かしさを誘う。薄く切って冷やすもよし、ブランデーのおともにもよし。●岐阜県大垣市俵町39  0584-78-2111(俵町本店)
0584-78-2111(俵町本店)
 0584-78-2111(俵町本店)
0584-78-2111(俵町本店)
RELATED STORY

ああ!昭和の味!小津安二郎が愛した焼き鳥の「伊勢廣」

水ようかん評論家
向田邦子のとっておき
「新茶の出るころから店に並び、
うちわを仕舞う頃にはひっそりと姿を消す、
その短い命がいいのです」
(講談社文庫『眠る盃』所収「水羊羹」より)
薄墨色の美しさと、するんとした喉ごし、口の中に余韻が残る程度のほの甘さ。自らを〝水羊羹評論家”〟と称した向田邦子が毎年心待ちにしていたのは、東京・青山『菊家』の水羊羹です。
帳場を兼ねたガラスケースにこの菓子が並ぶのは、桜の青葉が出る季節のみ。エッセイ「水羊羹」にも書いたように、白磁のそばちょこに京根来の茶卓を出て、すだれ越しの自然光か、少し黄色っぽい電灯の下で食べるのが向田流でした。短期間だけの味だからこそ、美学をもって楽しんだのでしょう。
今も変わらず季節限定の味を守る『菊家』。めまぐるしく変わり続ける街にあって、そこだけ昭和の風が吹いているような店構えにもなごみます。

うちわを仕舞う頃にはひっそりと姿を消す、
その短い命がいいのです」
(講談社文庫『眠る盃』所収「水羊羹」より)
薄墨色の美しさと、するんとした喉ごし、口の中に余韻が残る程度のほの甘さ。自らを〝水羊羹評論家”〟と称した向田邦子が毎年心待ちにしていたのは、東京・青山『菊家』の水羊羹です。
帳場を兼ねたガラスケースにこの菓子が並ぶのは、桜の青葉が出る季節のみ。エッセイ「水羊羹」にも書いたように、白磁のそばちょこに京根来の茶卓を出て、すだれ越しの自然光か、少し黄色っぽい電灯の下で食べるのが向田流でした。短期間だけの味だからこそ、美学をもって楽しんだのでしょう。
今も変わらず季節限定の味を守る『菊家』。めまぐるしく変わり続ける街にあって、そこだけ昭和の風が吹いているような店構えにもなごみます。

菊家
昭和10(1935)年、青山・骨董通り沿いに開店した菓匠。こぢんまりした店内には、向田がエッセイ『水羊羹』に著したとおり、「緋(ひ)毛(もう)氈(せん)をあしらった待合の椅子」が置かれている。上質な小豆の香りを生かした水ようかんは、店の奥の小さな工房で手づくりされている。毎年5月上~中旬の、桜の青葉が出る時期を待って店頭に並ぶ。●東京都港区南青山5-13-2  03-3400-3856
03-3400-3856
 03-3400-3856
03-3400-3856
くずもちのはかなさを
愛でた中里恒子
「葛もちほどにふりふりせず、
やわらかいとろけるやうな口當りと、
ちよつと焦がしたきな粉で
くるんである香ばしさ」
(作品社『日本の名随筆24 茶』所収
「和菓子曼まんだら」より)
「日持ちのする菓子は飽きる」と綴った作家・中里恒子。彼女が愛したのは、日本橋の老舗『長門』の久寿もち(くずもち)です。葛ではなく、わらび粉と砂糖で練り上げたそれは、昭和初期に先代が始めたもの。優しい甘みのわらびもちに、甘さのないきなこをたっぷりかけていただくと、昭和の味が口中に広がります。
皿の上でぷるぷる揺れるさまと、懐かしいきなこの香り。とろける食感や風味が、一日二日で消えてしまうところも、中里の美意識にかなったようです。包装紙には葵の紋。『長門』が代々徳川家の菓子司だったことを伝えます。

やわらかいとろけるやうな口當りと、
ちよつと焦がしたきな粉で
くるんである香ばしさ」
(作品社『日本の名随筆24 茶』所収
「和菓子曼まんだら」より)
「日持ちのする菓子は飽きる」と綴った作家・中里恒子。彼女が愛したのは、日本橋の老舗『長門』の久寿もち(くずもち)です。葛ではなく、わらび粉と砂糖で練り上げたそれは、昭和初期に先代が始めたもの。優しい甘みのわらびもちに、甘さのないきなこをたっぷりかけていただくと、昭和の味が口中に広がります。
皿の上でぷるぷる揺れるさまと、懐かしいきなこの香り。とろける食感や風味が、一日二日で消えてしまうところも、中里の美意識にかなったようです。包装紙には葵の紋。『長門』が代々徳川家の菓子司だったことを伝えます。

長門
創業は18世紀前半の享保年間。店は東京駅のほど近くに立ち、菓子はすべて建物内の工房でつくられる。小津安二郎や古今亭志ん朝も、この店の美しい生菓子や半生菓子のファンだった。昭和初期の関東では、わらびもちが一般的でなかったため、なじみのある「久寿もち」の名をつけた。竹の包みを開けると、三角形にカットしたものが12切れ。冷蔵庫で15分ほど冷やすとおいしさが増す。夕方には売り切れることも。●東京都中央区日本橋3-1-3  03-3271-8662
03-3271-8662
 03-3271-8662
03-3271-8662
京都『麩嘉』の
麩まんじゅうを絶賛した獅子文六
「麩屋へ出かけて、
店頭でできたてのを食ったら、
一番うまいのではないかと思う」
(文春文庫『食味歳時記』より)
「ふまんじゅうを一番上手につくる」と、作家・獅子文六(ししぶんろく)が記した京都の「麩嘉(ふうか)」本店は、日本で最も古いといわれる生麩店。代々御所に献上し、今も料理屋に卸す生麩づくりが専門です。
その日使う分だけ手づくりして売る…という哲学ゆえ、麩まんじゅうの購入は予約のみ。むっちりつるんとした食感も上品な香りも、この本店でしか得られません。商家らしいのれんをくぐり、水を打った石の床がひんやりとする店内に足を踏み入れれば、とっておきの美味への期待が高まります。

店頭でできたてのを食ったら、
一番うまいのではないかと思う」
(文春文庫『食味歳時記』より)
「ふまんじゅうを一番上手につくる」と、作家・獅子文六(ししぶんろく)が記した京都の「麩嘉(ふうか)」本店は、日本で最も古いといわれる生麩店。代々御所に献上し、今も料理屋に卸す生麩づくりが専門です。
その日使う分だけ手づくりして売る…という哲学ゆえ、麩まんじゅうの購入は予約のみ。むっちりつるんとした食感も上品な香りも、この本店でしか得られません。商家らしいのれんをくぐり、水を打った石の床がひんやりとする店内に足を踏み入れれば、とっておきの美味への期待が高まります。

麩嘉(府庁前本店)
京料理に欠かせない生麩をつくり続ける老舗。のれんを掛けた店の横には井戸水が湧いていて、生麩づくりにも使われる。今も、近所の住民が水を汲みにくる姿が見られる。生麩が好きだった明治天皇の要望で、先々代が考案したという麩まんじゅうは、青海苔の粉が練り込まれた風味豊かな生麩でこし餡を包み、笹の葉でくるんだもの。餡には丹波の大納言小豆を使用。予約でのみ購入可能。●京都府京都市上京区西洞院椹木町上ル  075-231-1584
075-231-1584
 075-231-1584
075-231-1584
RELATED STORY

六本木・泉屋博古館分館で、伊藤若冲のメジロオシを鑑賞する絶好の機会

女優・沢村貞子が愛した
目黒『八雲』のもち菓子
1974年4月10日
おやつ ちもと もち
1974年4月11日
おやつ ちもと 半生菓子
1974年4月15日
おやつ ちもと わらびもち
(『献立日記』より)
毎日の食事は朝夜の2食だけ。菓子や果物などのおやつを昼食代わりにしていたのが、昭和の名女優・沢村貞子。彼女がつけていた「献立日記」には、「御菓子所ちもと」の菓子が何度も登場します。
そのひとつが、昭和40(1965)年に初代店主が考案した写真の八雲もち。まず、竹皮のこの包みに郷愁を誘われます。中にはマシュマロのような弾力の求肥もち。コクのある黒砂糖と砕いたカシューナッツが入っているのが特徴です。
餅の素材から包みに至るまで、50年間一切変わりなし。価格も手ごろな愛すべきおやつです。

おやつ ちもと もち
1974年4月11日
おやつ ちもと 半生菓子
1974年4月15日
おやつ ちもと わらびもち
(『献立日記』より)
毎日の食事は朝夜の2食だけ。菓子や果物などのおやつを昼食代わりにしていたのが、昭和の名女優・沢村貞子。彼女がつけていた「献立日記」には、「御菓子所ちもと」の菓子が何度も登場します。
そのひとつが、昭和40(1965)年に初代店主が考案した写真の八雲もち。まず、竹皮のこの包みに郷愁を誘われます。中にはマシュマロのような弾力の求肥もち。コクのある黒砂糖と砕いたカシューナッツが入っているのが特徴です。
餅の素材から包みに至るまで、50年間一切変わりなし。価格も手ごろな愛すべきおやつです。

御菓子所ちもと
現在は軽井沢にある戦前からの名店「ちもと本家」から、昭和40年にのれん分けされた和菓子屋。コクのある国産黒砂糖を使用した八雲もちは、1日1000個ほどが夕方前に売り切れることも。独特の食感は、泡立てた卵白を寒天で固めた〝淡雪〟を求肥に混ぜてつくるもの。竹皮包みを留める紙縒り(しより)まで、今でも手作業でつくっている。沢村は、季節のわらびもちや桜もち、じょうよまんじゅうも好んで求めた。●東京都目黒区八雲1-4-6  03-3718-4643
03-3718-4643
 03-3718-4643
03-3718-4643
川端康成のお気に入りは
愛らしいフランス菓子
「全くフランスでも滅多に味へない
本格的な良心的な作品であると感じる」
(『フランス菓子カド』推薦文より)
西洋への憧れを形にしたような、愛らしいひと口菓子、プチ・フール。バタークリームのミルキーな甘さと洋酒の香りが広がる子の菓子は、昭和35(1960)年創業のフランス菓子店『カド』の看板商品です。
考案したのはパリで修業を積んだ創業者の髙田壮一郎。文豪・川端康成は、その洒落たデコレーションや品よい甘さを大層気に入り、「心底から私をよろこばせる」と讃えました。
今も、味わいや姿は当時のまま。洋画の飾られた喫茶室で、コーヒーとともにいただくのも素敵です。

本格的な良心的な作品であると感じる」
(『フランス菓子カド』推薦文より)
西洋への憧れを形にしたような、愛らしいひと口菓子、プチ・フール。バタークリームのミルキーな甘さと洋酒の香りが広がる子の菓子は、昭和35(1960)年創業のフランス菓子店『カド』の看板商品です。
考案したのはパリで修業を積んだ創業者の髙田壮一郎。文豪・川端康成は、その洒落たデコレーションや品よい甘さを大層気に入り、「心底から私をよろこばせる」と讃えました。
今も、味わいや姿は当時のまま。洋画の飾られた喫茶室で、コーヒーとともにいただくのも素敵です。

フランス菓子 カド
川端と親交のあった洋画家・髙田力蔵の息子・壮一郎が創業。川端はこの店のクッキーも大好きで、土産にもらうと缶ごと文机の下に置いてひとり占め。家族にも分けなかったという。ひと口サイズのプチ・フールは、オレンジリキュールや西洋山ハッカの薬草酒など、洋酒を使用した大人の味。店の奥の工房で、ひとつひとつていねいに手づくりされている。●東京都北区西ヶ原1-49-3  03-3910-6241
03-3910-6241
 03-3910-6241
03-3910-6241
RELATED STORY

名水に育まれ洗練された「京都の冷奴」名店巡り
まだまだあります!
作家たちを虜にした
甘くて懐かしい〝昭和のおやつ〟
小説や随筆をしたためる原稿用紙の傍らには、あんこ菓子やハイカラな洋菓子が欠かせない――そんな作家たちが愛した昭和のおやつが勢ぞろい。お取り寄せ可能なものや、包みの魅力的なものが多く、手土産にも喜ばれることうけあいです。

三宅艶子が愛した
『ローザー洋菓子店』のクッキー
ハンドメイドのハイカラ・レトロな缶に、バターと粉の香り豊かなクッキーがぎっしり。サクサクと懐かしい手づくりの味を愛したのは、東京生まれ東京育ちの小説家・三宅艶子(みやけつやこ)です。「東京の菓子」(『東京味覚地図』に寄稿)で、夜中の執筆のおともとして挙げています。販売は店頭でのみ、数日前の予約が確実です。
●東京都千代田区麴町2-2 03-3261-2971
03-3261-2971
●東京都千代田区麴町2-2
 03-3261-2971
03-3261-2971 
三島由紀夫が愛した
『日新堂菓子店』のマドレーヌ
厚手のアルミカップに入った姿と甘い香りが懐かしい、リッチな味の焼き菓子。三島由紀夫は昭和39年から毎夏、下田の海でバカンスを過ごし、執筆にも勤しみました。彼が愛したのが、創業大正11(1922)年の「日新堂菓子店」。週に一度は訪れ、「日本一のマドレーヌですよ」と周囲の人々に声をかけていたほどの贔屓ぶりだったとか。取り寄せも可能です。
●静岡県下田市3-3-7 0558-22-2263 http://nisshindoshop.weebly.com/
0558-22-2263 http://nisshindoshop.weebly.com/
●静岡県下田市3-3-7
 0558-22-2263 http://nisshindoshop.weebly.com/
0558-22-2263 http://nisshindoshop.weebly.com/
林芙美子が愛した
『三野屋』の継続だんご
淡泊な甘みと、ひと口大のだんごが連なるかわいい姿。昭和の子供に持たせたら似合いそうな、上越生まれの名物が『三野屋(みのや)』の継続だんご。作家・林芙美子が愛し、名作『放浪記』にも登場させたことで一躍有名になりました。白餡を丸めて串にさし、表面を香ばしく焼いた素朴な味は、100年以上変わらない製法でつくられています。取り寄せも可能です。
●新潟県上越市中央1-1-11 025-543-2538
025-543-2538
●新潟県上越市中央1-1-11
 025-543-2538
025-543-2538
種村季弘が愛した
『伊勢屋』と『虎の門 岡埜栄泉』の大福
「あんこが食べたい。豆大福が食べたい。(略)東京に出るとわざわざ深川まで行って塩大福を買って帰ったりする」と、エッセイ『雨の日はソファで散歩』に綴った作家・種村季弘(たねむらすえひろ)。下町は門前仲町の駅近く、深川不動尊への参拝客で賑わう『伊勢屋』の塩大福(写真左)は、どっしり大ぶりな庶民のおやつ。北海道の小豆とザラメによる素朴な甘さが種村を喜ばせました。
先のエッセイは「芝の岡埜栄泉の甘みを抑えた豆大福──」と続きます。『虎の門 岡埜栄泉(とらのもん おかのえいせん)』の豆大福(写真右)は、食通をも黙らせる手土産として不動の人気を誇ります。エプロンに三角巾の女性が慣れた手つきで包んでくれるその大福は、つきたての餅にこし餡がたっぷり。塩っけのある赤えんどう豆との食べ合わせも実にいい! 開店前から客が並び、昼過ぎに完売することもある逸品です。
●『伊勢屋』東京都江東区富岡1-8-12 03-3641-0695 http://www.iseya.ne.jp/
03-3641-0695 http://www.iseya.ne.jp/
●『虎の門 岡埜栄泉』東京都港区虎ノ門3-8-24 03-3433・5550
03-3433・5550
先のエッセイは「芝の岡埜栄泉の甘みを抑えた豆大福──」と続きます。『虎の門 岡埜栄泉(とらのもん おかのえいせん)』の豆大福(写真右)は、食通をも黙らせる手土産として不動の人気を誇ります。エプロンに三角巾の女性が慣れた手つきで包んでくれるその大福は、つきたての餅にこし餡がたっぷり。塩っけのある赤えんどう豆との食べ合わせも実にいい! 開店前から客が並び、昼過ぎに完売することもある逸品です。
●『伊勢屋』東京都江東区富岡1-8-12
 03-3641-0695 http://www.iseya.ne.jp/
03-3641-0695 http://www.iseya.ne.jp/●『虎の門 岡埜栄泉』東京都港区虎ノ門3-8-24
 03-3433・5550
03-3433・5550
井上靖が愛した
『森八』の長生殿
「風味絶佳(ふうみぜっか)」という言葉がふさわしい、紅と白の美しい菓子。作家・井上靖が心を寄せ、帰省の度に母への手土産として選んだのが、加賀藩御用菓子の歴史を誇る『森八(もりはち)』の干菓子、長生殿(ちょうせいでん)。口の中でほろほろほどける落雁(らくがん)は、阿波の和三盆糖に秘伝の精粉を合わせてつくる日本三名菓のひとつです。取り寄せも可能。
●石川県金沢市大手10-15 076-262-6251 http://www.morihachi.co.jp/
076-262-6251 http://www.morihachi.co.jp/
●石川県金沢市大手10-15
 076-262-6251 http://www.morihachi.co.jp/
076-262-6251 http://www.morihachi.co.jp/
團伊玖磨が愛した
『石橋屋』の仙台駄菓子
きなこねじり、みそぱん、かるめら焼――「駄菓子屋の店先は、そとを通っただけでも黒砂糖のにおいがした」(『舌の上の散歩道』朝日文庫より)。作曲家の團伊玖磨(だんいくま)が仙台へ出かけた際に寄ったのは、仙台駄菓子の名店『石橋屋』。後日、果物ゼリー菓子を取り寄せたことも記されています。写真は郷土駄菓子の詰め合わせ。取り寄せも可能です。
●宮城県仙台市若林区舟丁63 022-222-5415 http://www.ishibashiya.co.jp/
022-222-5415 http://www.ishibashiya.co.jp/
●宮城県仙台市若林区舟丁63
 022-222-5415 http://www.ishibashiya.co.jp/
022-222-5415 http://www.ishibashiya.co.jp/